本文
図書館まわりの水辺について考えるWSを開催しました(第一中学校編)
ワークショップ(WS)の取組みの概要
復興まちづくり事業
平成29年台風第18号を受け、市中心部は河川氾濫等により甚大な浸水被害に見舞われました。今後、同じような被害を受けないために、大分県によって津久見川・彦の内川において、河床掘削や拡幅工事等の復興に向けた取組が進められています。
これに伴い、津久見市としても、災害のみならず、津久見川周辺における今後のまちづくりに対するあり方を広く考える必要があると捉え、大分県から補助を受けながら川を中心としたにぎわいの創出や地域コミュニティの活性化、定住促進を目的とした「復興まちづくり事業」(事業主体:津久見市周遊活性化対策協議会)を立ち上げました。本事業の内容は、大きく下記の3点です。
---------------------------------------------------
【(1)住民WSやイベントの実施 : WSやイベントを通じて水の恐ろしさと水辺の楽しさの両面を学び、今後の河川利用のあり方を模索する】
【(2)周遊移動環境・にぎわいエリアの整備 : 津久見の特色を活かし、周遊を促すマップの作成と、桜等の植樹やその周辺整備を検討する】
【(3)移転コーディネート : 津久見市内で転居を検討している方に対するフォローアップとして相談会等を開催する】
---------------------------------------------------
※このうち、今回の第一中学校を対象としたWSは「(1)住民WSやイベントの実施」にあたります
第一中学校を対象としたWS
題目:図書館まわりの水辺について考えよう!
日時:令和元年7月8日(月)13:10~15:00
対象:津久見市立第一中学校 1年生3クラス
内容:図書館や図書館周辺の水辺空間の利活用について考える
------------------------------------------------------
中学校の生徒は事前学習として津久見市や復興に関する調べ学習を行い、
図書館周辺や津久見川でできることについて考え、今回のWSを迎えています。
.
WSでは台風第18号災害の状況を振り返り、その後の復興に向けた取組みを学びました。
その後、津久見川・彦の内川の河川改修工事の概要や津久見川沿いのまちづくり計画についても学びました。

.
NPO法人まちづくりツクミツクリタイの高瀬理事長にお越しいただき、「水育」という観点から水を中心とした
自然環境を守るために、私たち一人ひとりにできることはなんだろう?ということについてお話しいただきました。
そして、福岡大学工学部社会デザイン工学科 景観まちづくり研究室の樋口さんから、水辺空間の活用事例について、
他県の事例を用いながら、水辺空間の使い方の良い事例をご紹介いただきました。
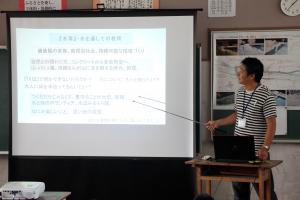
.
グループ作業では、生徒たちは各班に分かれ、図書館周辺の図面を広げて
これまでに図書館周辺でやったことのあることや普段の利用状況、好きなことや問題点
について書き記していきました。
.
図書館周辺でこれからやってみたいことや、あったらいいなと思うものなども
みんなで楽しく意見を出し合い、想像を膨らませていきます。
.
班ごとに出された意見を、クラスのみんなに発表しました。
発表の中では、これまでに「読書」「勉強」「部活で走る」「水遊び」「ダンス」などをしたことがある。
「水がない」「雑草が多い」「虫が多い」などの問題点や「ウォータースライダー」「カフェ」
「屋台」「イルミネーション」「桜」「花壇」「ベンチ」が欲しい、「BBQ」「水遊び」「花見」がしたいなど
様々な意見が出されました。
.
WSの翌日、中学校では3クラスそれぞれで出された意見を共有する時間が設けられ、
みんなのアイディアを確認し合っています。
.
来月には第一中学校1年生の代表生徒に地域の方を加えて、
再度図書館周辺の活用方法について、より具体的に検討していきたいと考えています。
生徒たちが図書館や水辺空間を親しみ持って利用してもらえるように、
周辺整備等できることを検討していきたいと思います。








