本文
孤独・孤立ってなに?
執筆者 同志社大学社会学部教授 永田 祐 氏
津久見市孤独・孤立支援ホームページ作成にあたり、同志社大学社会学部教授 永田 祐(ながた ゆう)氏に執筆していただきました。
永田教授には、令和3年11月13日に開催された「津久見市制施行70周年記念シンポジウム」において、「つくみの未来へつなげよう ~地域共生社会の実現に向けて~」をテーマにご講演をいただいています。

【プロフィール】
永田 祐(ながた ゆう) 同志社大学 社会学部 教授
慶應義塾大学政策・メディア研究科修士課程修了。
上智大学文学研究科社会学専攻博士後期課程修了。博士(社会福祉学)。
日本学術振興会特別研究員、立教大学助手、愛知淑徳大学専任講師を経て現職。英国ブリストル大学客員研究員(2013年3月~2014年3月)。社会福祉士として成年後見活動も行っている。
厚生労働省「成年後見制度利用促進専門家会議」委員、「地域における住民主体の課題解決力強化・相談支援体制の在り方に関する検討会」構成員などを務めるとともに、様々な自治体の地域福祉計画などの策定委員を務める。
主な著書として『包括的な支援体制のガバナンス』(有斐閣、2021年。2022年度日本社会福祉学会学会賞学術賞、第24回SOMPO福祉財団賞)がある。
(主な著書)
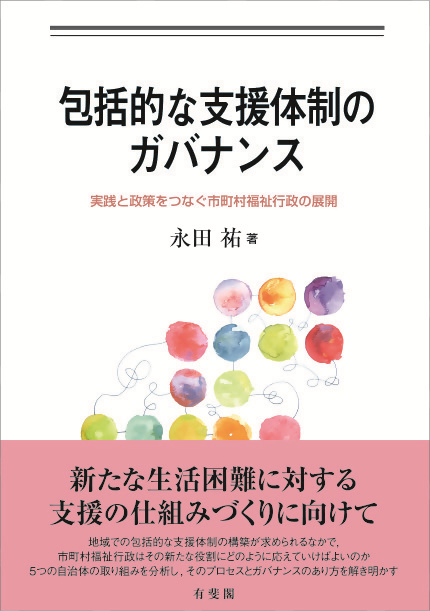
孤独・孤立ってなに?
孤独は主観的状態、孤立は客観的状態と言われています。例えば、私がひとりぼっちだと感じているとすれば、実際は多くの友人に囲まれていても、孤独を感じていることになります。一方、人とのつながりが客観的にない状態、極端な例を挙げれば、話をしたり、相談できる人が一人もいなければ、孤立しているということになります。
どうして孤独・孤立の対策が必要なの?
よくある誤解は、「孤独や孤立は本人が望んでいるのだから、他人がとやかく言うことではない」とか「よい孤独や孤立もある」というものです。確かに人の生き方に社会があまり介入しすぎることは問題です。また、長い人生の中では、一人で自分と向き合う時間が必要な時もあるでしょう。しかし、家族や地域社会、そして安定した雇用といったこれまでの日本社会の基盤が揺らぐ中で、望んでいても人とのつながりを持つことができず、誰にも頼れない人が看過できなくなっているところに現在の孤独・孤立の問題があります。
では、こうした問題を放置することがどのような問題につながるのか考えてみましょう。強い孤独感や孤立した状態が、身体の様々な不調と関係することは、様々な研究から明らかになっており、最近では要介護のリスクや寿命の短さと関連していることも指摘されています。さらに、孤独や孤立が深刻になると、自分が誰にも必要とされていないという感覚が強くなり、最悪の場合、自殺や孤独(孤立)死といったことにつながる可能性があります。
孤独・孤立対策のために地域でできること
こうした問題が認識されるようになり、政府としても様々な対策を打ち出すようになってきました。もちろん、こうした取組は大変重要ですが、よく考えてみると、人とのつながりの問題である孤独・孤立対策は、地域社会の中でこそできることがたくさんあります。大切なのは、ひと言でいうと「居場所と出番のある地域社会」。居場所とは、ここにいてもよいと感じられて、人と話し、つながりを作ることができる安心できる場所のことです。出番は、文字通り、役割を発揮して活躍できる機会のことです。地域の中に、安心できる居場所があって、自分が必要とされる出番があることで、孤独・孤立を予防し、その状態を改善することができます。
津久見市民へのコメント
新型コロナウィルスの流行は、孤独・孤立の問題をいっそう深刻にしました。しかし、改めて私たちが人とのつながりの中で生きていること、その大切さを実感することにもなったのではないかと思います。
高齢になったり、病気になったり、障害があったとしても、私たちには自分の存在を認められる「居場所」と人から必要とされる「出番」が必要です。地域の中にそんな居場所がたくさんあって、色々な立場の人が役割を持って活躍できる、そんな地域社会を作っていきましょう。もちろん、こうした取組は、地域包括支援センターや社会福祉協議会といった専門職と協力して取り組むことが大切です。専門職の力を引き出して、地域づくりを進めていきましょう。





